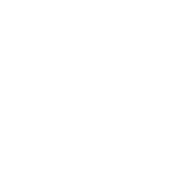泡盛の魅力と可能性を語る、ムック本刊行記念トークイベント

去った2月16日(日)、那覇市にあるジュンク堂書店で「もっと知りたい、泡盛のこと。」刊行記念トークイベントが開催された。
トークに参加したのは、瑞泉酒造で泡盛の製造を担当する伊藝壱明さん、バーテイスティングクラブの店主・儀部頼人さん、南島酒販株式会社の古謝雄基さん。本誌の中でも登場してくれた泡盛愛溢れる3名に、泡盛の魅力や、未来の可能性について語ってもらった。
本誌のテーマでもある「ハードリカーとしての泡盛の魅力」について、ワインをはじめとした他のお酒との違いとして、香りの幅広さや、時間の経過とともに香りが変化する点が泡盛の魅力の一つだと語る3人。ここ数年、徐々に県外での泡盛の注目度も上がってきていると感じているという。
バー店主として、日々さまざまなお客さんに泡盛の魅力を伝えている儀部さんは、泡盛の注目度について、「世界的なジャパニーズウイスキーの人気の高まりがある一方で、ウイスキーの価格高騰により、新たな蒸留酒を求める動きも出てきていると感じます。ウイスキー専門誌『ウイスキーガロウ』の編集長でもある土屋守さんは最近泡盛に注目しており、雑誌内でも特集記事が何度も組まれている。また、海外市場でも動きがあり、日本人が経営する飲食店や、特にシンガポールやマレーシアなどアジア市場で泡盛の販売が進められています。だからこそ、単に安価なものを売るのではなく、本当に価値のあるものを紹介することが大事だと思いますね」とのこと。

日々、数多くの酒類を県内外で販売している古謝さんは、泡盛の市場には、一般的によく飲まれている30度帯の泡盛と、40度帯の高度数帯の2つの市場があり、後者は、バーでの需要を拡大できる可能性を秘めていると考えている。
「泡盛を含む焼酎市場では、黒霧島のような巨大ブランドとの競争は厳しいが、40度帯の泡盛はまだまだ未開拓の市場。インバウンド需要の増加やユネスコ無形文化遺産登録の影響で、泡盛がカクテルのベースとして注目される可能性が高い」と古謝さん。バーでは、高アルコールのスピリッツが好まれる傾向がある。そのため40度帯の泡盛はそのニーズに合致しているのだ。特に海外のお客さんは高アルコール度数を求めることが多いため、泡盛が日本の代表的なスピリッツであるとして、海外市場に進出していくという可能性も秘めている。

泡盛を造る立場である瑞泉酒造の伊藝さんは、今後の泡盛市場の展開を踏まえ、泡盛製造についてどう捉えているのだろうか。
「泡盛業界は、実験的な泡盛をつくるブランド『shimmer』や、3回蒸留の『尚』をはじめ、これまでになかった蒸留方法などの新しいアプローチの仕方が、他の業界から注目されるようになったと感じています。自分たちが行っていることが革新的であるとは意識していませんでしたが、他者からは評価されていることを実感していますね。僕は、お酒の味を評価する際、華やかな香り、甘さ、オイリーさ(余韻)のバランスが重要だと思っていて、このバランスをうまく調整することで、異なる味わいを作り出せる可能性があると感じています。今後もより多様な泡盛の香りや味を表現したいですね」
本誌でも紹介している新しい泡盛のブランド「shimmer」は、まさに泡盛業界の未来の扉を開く一つの鍵となりそう。「いくつもシリーズが増えていくにつれ、泡盛業界の中でも受け入れられ、shimmerが登場してから業界内の雰囲気が少し変わった気がしますね」と伊藝さん。
さまざまな変化の中で、蒸留酒業界でも注目を浴びはじめている泡盛。今回はそんな泡盛の魅力の一端に触れるイベントとなった。今後さらに日本中や世界へ伝わっていく泡盛の魅力、更なる展開を期待したい。